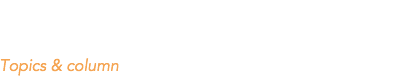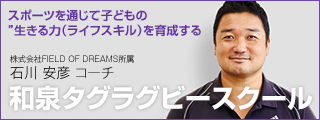- TOP
- トピックス・コラム一覧
- 「リスペクト」を育む指導
「リスペクト」を育む指導
2018/01/05
子どもにスポーツを習わせる理由として「礼儀正しくなってほしいから」と言う親御さんが多くいます。
確かに高校野球を筆頭に、日本の青少年のスポーツ場面を見ていると「おねがいします」「ありがとうございました」と始終、頭を下げている場面をみかけます。だから「スポーツをする人は常にあのように常に礼儀正しく振る舞うもの」というイメージが定着しているのかもしれません。
でも、各競技の国際大会やオリンピックを観戦していて、日本以外の国の選手が、試合会場で方々に頭を下げているシーンを見たことがある人はいないはずです。あのようにスポーツ選手が何かにつけてあちこちに礼をするという習慣は、世界広しといえども日本独特のものです。
対戦相手、あるいは大会関係者をリスペクトする気持ちを表すことは大変素晴らしいことですので、礼をする行為そのものを否定するつもりはありません。しかし、あのように常にチーム一同が一糸乱れず同じタイミング、同じ口調でまるで「儀式」のように礼を乱発している様子を見ると、一つ一つに本当に「礼をする気持ち」がこもっているのか、と心配になります。
高校野球・甲子園大会が近づくと、毎年、出場停止、謹慎といった処分を下されるチームが取り沙汰されます。その多くが暴力、喫煙、飲酒、万引きが原因です。大学生アスリートが集団で痴漢行為や性的暴行をして逮捕される事件もありました。人一倍、礼儀正しく品行方正であるはずの選手たちが、反社会的な行為をして咎められています。
考えてみれば、スポーツ界では今でも、一学年違えば先輩の言うがまま、後輩は理不尽なことを強要されても耐えるのみ、といった前近代的な上下関係がまかり通っています。絶対的権限の下、まるで暴君のように振る舞っている監督、コーチがいます。「勝つために」という目標の下、一般社会の常識とはかけ離れた価値観が「当たり前」のこととして共有されている世界があります。
そういう独特の価値観がある世界で慣行されている「礼」の方法が、果たして日常生活に本当に役に立っているのか、見直すことも必要でしょう。
私がかかわる少年サッカーでも、多くのチームがグラウンドに礼、本部席に礼をして会場入りし、試合では相手に礼、審判に礼、相手ベンチに礼をします。そして、帰る時にも再び本部に礼、グラウンド礼をします。一日計7回も礼をしています。しかしグラウンドを出てしばらくして、町中で私が「こんにちは」と微笑みかけても、「何だ、このおじさん」といわんばかりの怪訝な顔をして応答してくれない子がいるのです。
「スポーツの礼儀正しさ」が、ある設定、ある場面、に限定されたものになってしまい、一般の社会生活に応用されないようでは意味がありません。心から相手をリスペクトする気持ちに裏付けられていなければ、形だけの儀式になってしまいます。
スポーツとは、知力、体力の限りを尽くして相手を攻略し、打ち負かす行為です。格闘技では相手を傷つけることが目的になることさえあります。ルールに反しないギリギリのところで手を尽くして相手を屈服させようとする戦いなのですから「そういう大変なことにつき合ってくれてありがとう」という気持ちがなければとてもやってはいけません。そういう精神をきちんと身につけていれば、集団で強要されずとも自ずとリスペクトの態度が示されるでしょう。
その意味で、指導者も親も「いかにして勝つか」ということばかり教え、形式的な礼を繰り返させるばかりでなく「スポーツすることの意味」を伝えてほしいと思います。
--
投稿者:永井洋一
※プロフィール
スポーツジャーナリスト。特定非営利活動法人・港北フットボールクラブ代表。取材執筆、CS放送「プレミアリーグ」解説などメディア関係の活動を推進する傍らサッカーコーチ活動を30余年継続し、草の根のスポーツ活動の現場感覚を体感しつつジャーナリスト活動に繁栄させていいる。また、青少年の育成とスポーツに関する論客としても活動し、著書の主張を基盤に各地で講演活動も行なっている。
確かに高校野球を筆頭に、日本の青少年のスポーツ場面を見ていると「おねがいします」「ありがとうございました」と始終、頭を下げている場面をみかけます。だから「スポーツをする人は常にあのように常に礼儀正しく振る舞うもの」というイメージが定着しているのかもしれません。
でも、各競技の国際大会やオリンピックを観戦していて、日本以外の国の選手が、試合会場で方々に頭を下げているシーンを見たことがある人はいないはずです。あのようにスポーツ選手が何かにつけてあちこちに礼をするという習慣は、世界広しといえども日本独特のものです。
対戦相手、あるいは大会関係者をリスペクトする気持ちを表すことは大変素晴らしいことですので、礼をする行為そのものを否定するつもりはありません。しかし、あのように常にチーム一同が一糸乱れず同じタイミング、同じ口調でまるで「儀式」のように礼を乱発している様子を見ると、一つ一つに本当に「礼をする気持ち」がこもっているのか、と心配になります。
高校野球・甲子園大会が近づくと、毎年、出場停止、謹慎といった処分を下されるチームが取り沙汰されます。その多くが暴力、喫煙、飲酒、万引きが原因です。大学生アスリートが集団で痴漢行為や性的暴行をして逮捕される事件もありました。人一倍、礼儀正しく品行方正であるはずの選手たちが、反社会的な行為をして咎められています。
考えてみれば、スポーツ界では今でも、一学年違えば先輩の言うがまま、後輩は理不尽なことを強要されても耐えるのみ、といった前近代的な上下関係がまかり通っています。絶対的権限の下、まるで暴君のように振る舞っている監督、コーチがいます。「勝つために」という目標の下、一般社会の常識とはかけ離れた価値観が「当たり前」のこととして共有されている世界があります。
そういう独特の価値観がある世界で慣行されている「礼」の方法が、果たして日常生活に本当に役に立っているのか、見直すことも必要でしょう。
私がかかわる少年サッカーでも、多くのチームがグラウンドに礼、本部席に礼をして会場入りし、試合では相手に礼、審判に礼、相手ベンチに礼をします。そして、帰る時にも再び本部に礼、グラウンド礼をします。一日計7回も礼をしています。しかしグラウンドを出てしばらくして、町中で私が「こんにちは」と微笑みかけても、「何だ、このおじさん」といわんばかりの怪訝な顔をして応答してくれない子がいるのです。
「スポーツの礼儀正しさ」が、ある設定、ある場面、に限定されたものになってしまい、一般の社会生活に応用されないようでは意味がありません。心から相手をリスペクトする気持ちに裏付けられていなければ、形だけの儀式になってしまいます。
スポーツとは、知力、体力の限りを尽くして相手を攻略し、打ち負かす行為です。格闘技では相手を傷つけることが目的になることさえあります。ルールに反しないギリギリのところで手を尽くして相手を屈服させようとする戦いなのですから「そういう大変なことにつき合ってくれてありがとう」という気持ちがなければとてもやってはいけません。そういう精神をきちんと身につけていれば、集団で強要されずとも自ずとリスペクトの態度が示されるでしょう。
その意味で、指導者も親も「いかにして勝つか」ということばかり教え、形式的な礼を繰り返させるばかりでなく「スポーツすることの意味」を伝えてほしいと思います。
--
投稿者:永井洋一
※プロフィール
スポーツジャーナリスト。特定非営利活動法人・港北フットボールクラブ代表。取材執筆、CS放送「プレミアリーグ」解説などメディア関係の活動を推進する傍らサッカーコーチ活動を30余年継続し、草の根のスポーツ活動の現場感覚を体感しつつジャーナリスト活動に繁栄させていいる。また、青少年の育成とスポーツに関する論客としても活動し、著書の主張を基盤に各地で講演活動も行なっている。